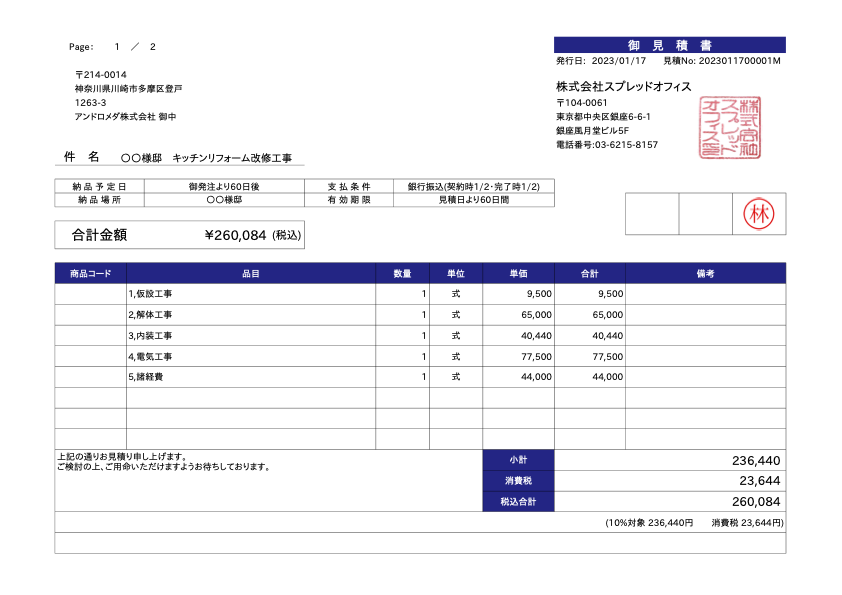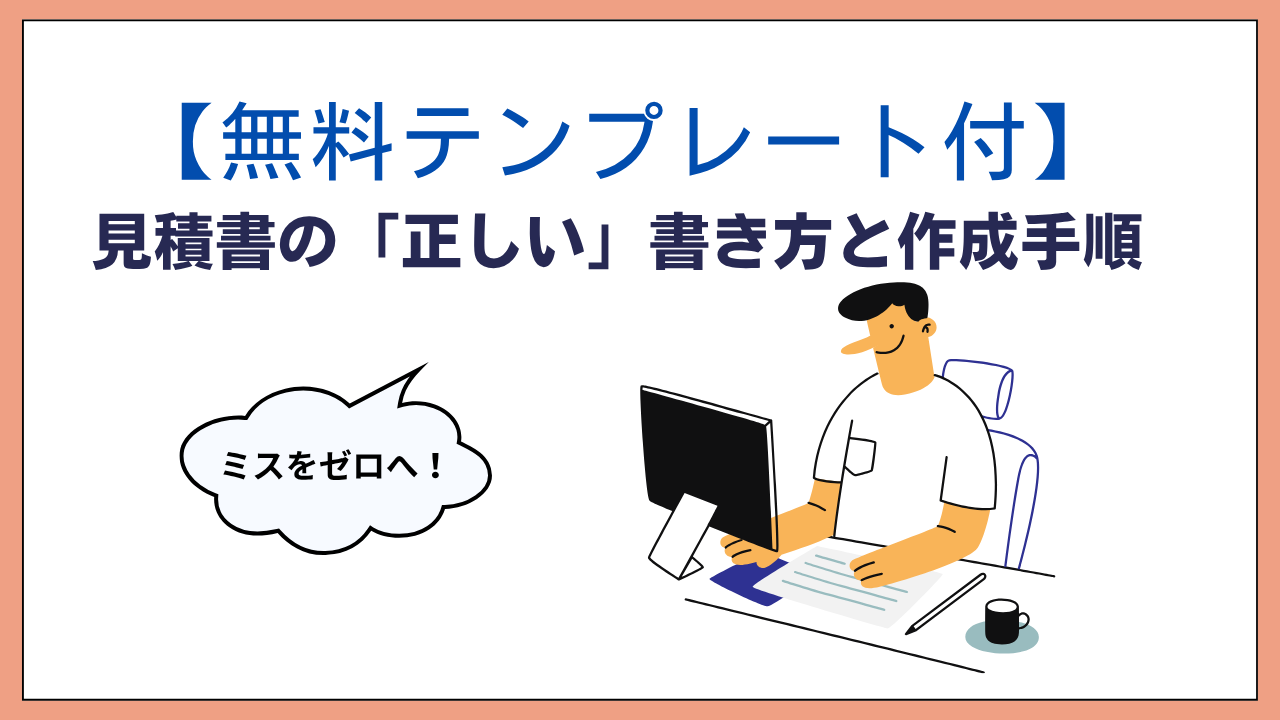「電子帳簿保存法(電帳法)」への対応は、すべての中小企業や個人事業主にとって避けて通れない課題です。特に、2024年1月からは「電子取引データ保存の義務化」が本格的にスタートし、違反した場合のリスクも高まっています。
この記事では、電子帳簿保存法の基本を「対象書類」「要件」「罰則」の3つのポイントに分けて、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。
電子帳簿保存法とは? 3種類の「対象書類」と保存のルール
電子帳簿保存法とは、税法で保存が義務付けられている帳簿や書類を、紙ではなく電子データで保存するためのルールを定めた法律です。
この法律の対象となる国税関係帳簿書類は、保存方法によって大きく以下の3種類に分類されます。
* 電子帳簿保存法の改正に伴い、2022年1月1日から2023年12月31日まで設けられた経過措置で、電子取引データの保存要件を満たせない「やむを得ない事情」がある場合に限り、書面での保存が認められる制度でした。
この宥恕措置はすでに終了しています。
罰則回避の鍵! 3つの保存区分に定められた「要件」
電子データを正しく保存し、税務調査で証拠能力を認めてもらうためには、データが「真実性」と「可視性」を持っていることを示す必要があります。
特に義務化された③電子取引データ保存で最低限守るべき「可視性」の要件は、次の通りです。
必須要件:電子取引データ保存で守るべきこと
電子取引で受け取ったデータ(PDFファイルなど)を保存する際は、以下の検索要件を満たす必要があります。
- 「取引年月日」
- 「取引金額」
- 「取引先」
上記の3項目で、保存データ(ファイル名や付随情報)を検索できるようにしておく必要があります。
真実性の確保: 上記の検索要件に加え、データの改ざん防止のために「タイムスタンプの付与」「訂正・削除の記録が残るシステム利用」「事務処理規程の備え付け」のいずれかを行う必要があります。
最も簡単なのは、「事務処理規程」を作成・備え付ける方法です。
電子帳簿保存法を守らない場合の「罰則」とリスク
電子帳簿保存法の要件を満たさずに保存義務を怠った場合、あるいはデータに関して不正があったと認められた場合、企業や事業主には以下のような重大なペナルティが科される可能性があります。
① 青色申告の承認取り消し
電子帳簿保存法に違反し、帳簿書類の保存義務を著しく怠ったと判断された場合、大きな優遇措置が受けられる青色申告の承認が取り消しになる可能性があります。
- 影響: 最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる、赤字(欠損金)の繰越控除ができなくなるなど、税負担が大幅に増加します。
② 重加算税の加重(追徴課税リスクの増加)
税務調査で、電子データ(スキャナ保存・電子取引)に関して隠蔽などの不正行為が発覚した場合、通常の重加算税(追徴課税額の35%)に加え、さらに10%が加重されます(合計45%)。
これは、不正を防止するための罰則強化措置です。
③ 会社法に基づく過料(最大100万円の罰金)
国税関係の帳簿書類の保存義務を適切に行わなかった場合、会社法の規定(第976条)に基づき、100万円以下の過料(行政罰)が科せられる可能性があります。
④ 経費・仕入税額控除の否認リスク
電子取引データを要件通りに保存していない場合、そのデータが税務調査で正式な証拠(証憑)として認められない可能性があります。
これにより、当該データに基づく経費や仕入税額控除が否認され、結果として追徴課税につながります。
今すぐ確認すべきこと(まとめ)
特に義務化されている「電子取引データ保存」に関しては、以下の2点を確認・実行しましょう。
- 保存ルール: 受け取った電子データ(PDFなど)を、「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にする。
- 改ざん防止: データの改ざんを防止するための事務処理規程を作成し、社内で運用する。
法令に沿った対応を確実に進めることで、罰則リスクを回避し、むしろデジタル化による業務効率化を実現することができます。